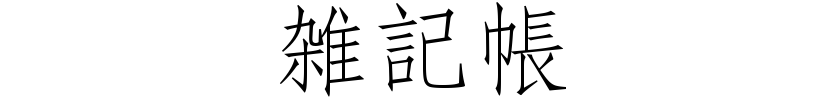2016/02/17
イーグルスの光と影
第一期イーグルス最期のアルバムとなった『ロング・ラン』のラストに収められた『サッド・カフェ』は美しい曲だ。
ドン・ヘンリーは僕たちは世界を変えることができると信じていたと歌う。しかし夢は破れ、サッド・カフェの片隅に埋もれている・・・。
叶わなかったイーグルスの夢とは、どのようなものだったのだろうか。
イーグルスは1971年結成された。リンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたのがきっかけだったが、寄せ集めのメンバーがそのままバンドを組んだ訳ではない。
グレン・フライにはバンドのあり方に明確な考えがあった。誰もが作曲できて、誰もが歌える、そんなバンドが作りたかった、そう後年グレン・フライは語っている。
つまり彼が作りたかったのは、一つのバンドというよりは、シンガー・ソングライターの自由な集まりだったのだ、そう私は解釈する。
70年代、シンガー・ソングライターという言葉には特別な重みがあった。歌を通して、自分自身の生を深く見つめていく者、そのような意味を持っていた。言葉を変えれば、個として生に向かう者、そんな意味を持っていた。
そのような独立した個が集まり、お互いに対等な立場で、一つの音楽を作る、それこそが、イーグルスの夢だったと私は思う。
そしてその夢は、60年代から70年代にかけて、アメリカだけでなく、世界中の若者たちが抱いた夢と重なる。誰もが対等で、支配する、支配されるという関係がない自由な社会。しかし若者たちの夢は、パワーが全てを動かす現実世界の中で崩れていった。
もちろんイーグルスも例外ではない。
プロデューサーのグリン・ジョンズは、セカンド・アルバムにおいて、自由な集まりで、音楽が多種多様というよりはバラバラという印象を与えかねないイーグルスに求心力を与えるべく、西部開拓時代のならず者の物語というコンセプトを与えた。それは音楽的に成功し、商業的には失敗した。
三枚目のアルバムの途中から、プロデューサーがビル・シムジクに変わった。それは前作の商業的失敗を受けてというよりは、グレン・フライが自分が目指していた自由な集まりとしてのイーグルスが夢なのだと気付き始めたからではないだろうか。
象徴的なのは、ドン・フェルダーの加入だ。彼は明らかにギタリストであって、シンガー・ソングライターではない。イーグルスの中で、リード−・ギターという役割ができてしまった。言葉を変えれば、イーグルスは個の自由な集まりから、一つのまとまりのあるバンドへと大きく舵を切ったのだった。
バンドへの転身は、四枚目のアルバムで、音楽的にも商業的にも成功を収める。このアルバムでは、自由な集まりとしてのイーグルスの顔も覗かせながらも、一つのバンドとしてのまとまりの方が印象強い。そのまとまりは、「支配する、支配されるという関係がない自由」を手放すことで、手に入れたものだっった、と私は思う。具体的にはグレン・フライとドン・ヘンリーが、イーグルスというバンドを支配した。
そしてもはやイーグルスが自由な集まりでないことを悟った、バーニー・レドンは、イーグルスを去っていく。
四枚目のアルバムのラストを飾る『安らぎによせて』でバーニー・レドンは、「夢が押し流されそうな時、君に愛を育む力を祈ろう」と歌う。この歌はグレン・フライへと向けられた餞別の歌のように、私は感じる。
おそらく彼は、グレン・フライがいつか自分が「love and freedom」で結ばれた集まりという夢を捨て、「バワーが全てを動かす現実」に身を任せたことに気付き、荒廃を味わうだろうことを予感していたのだろう。
それにしても、その荒廃を歌った『サッド・カフェ』は美しい。
写真のように、もう四人が「美しい海岸で(愛と自由に包まれて)みんな揃って会う」ことはないなら、せめて真夜中に夢が片隅で埋もれているサッド・カフェの椅子に身を沈めよう。