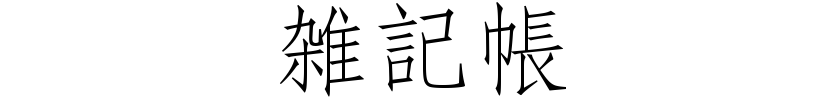現象学は、一つの哲学というより真理へと向かうための道具と言った方がいいかもしれまん。
現象学の創始者は、ドイツで研究生活を送ったフッサールという人ですが、彼は晩年弟子にこんな少年時代のエピソードを語っています。
ナイフをプレゼントされたが、よく切れないように見えたので、一生懸命に研いだ。しかし研ぐことだけに夢中になっていたので、ナイフの刃がどんどん小さくなっていくのに気づかなかった。
彼は現象学というナイフを生涯を通して研ぎ続けた、彼の膨大な研究を前にすると、そう感じます。
そこまで彼がこの現象学というナイフに夢中になったのは、彼がこのナイフこそが真理へと導いてくれると確信していたからです。確信していたからこそ、彼はナイフを鋭くするために生涯磨き続けました。
フッサールの情熱の核にあったものを知るには、遺作となった76歳の時(1935年)の著書『ヨーロッパの学問の危機と先験的現象学』(『危機書』)を手にするのがいいと思います。
前年にはヒトラーが首相になり、両親がユダヤ人の彼は研究を発表する術を失います。そしてやがてやって来る第二次世界大戦の影が大きくヨーロッパを覆っていました。
そうした状況下にあって、フッサールは、目覚ましい成果を挙げている自然科学を名指しして、危機にあると言うのです。
それは「われわれの不幸な時代において」、「この事実学(自然科学)は、われわれに何も語ってくれない」からです。
フッサールが『危機書』で述べていることから逆に彼の学問観が分かります。学問とは、本来、生の問題、生に意味はあるのか、無意味なのか、どう生きるのが正しいのか、そのような問いに応えるものだという学問観です。
彼は生の問題に学として、言い換えれば、誰もが理性的に納得できるあり方で、生の問題に応えようと生涯を捧げた人です。私はそう思います。そしてそのための道具が、現象学なのです。
現象学というと、判断中止(エポケー)だとか、現象学的還元だとか、指向性と構成とか、そんな用語ばかり目立ち、また取り上げられますが、根本にあるものを忘れては、まさに少年時代のフッサールのようになってしまうでしょう。